2025年度
教養講座「人生がちょっと豊かになるかもしれない香りの話」
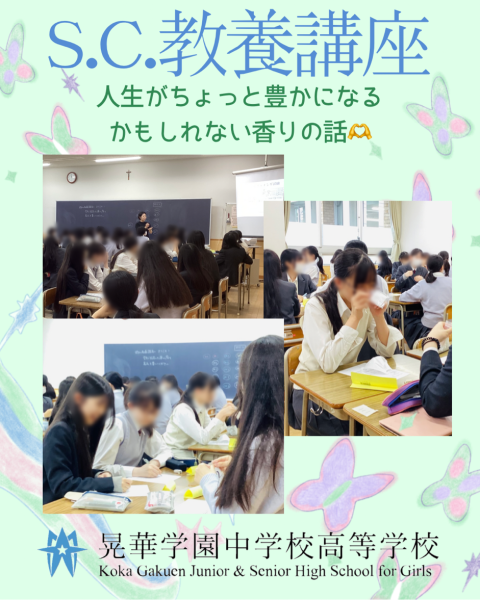
ソムリエの資格を持つ家庭科・情報科教員による香りの話。今年は「歌詞や物語の世界から香りを想像・創造する」をテーマにしました。

まずは2種類の香水を含ませたコットンを用意し、複合的な香りの中にどのような香りを感じるか、分析を行いました。
一つは針葉樹やレモンのような爽やかな香り、もう一つはリンゴとバニラの甘い香り。ちなみに前者は、中高生も知っているあの有名な曲の香水です。
「こっちがあの曲の香水の香りだよ」と伝えると、全員が大きく驚いていました!香りによって、歌詞に登場する女の子のイメージが随分変わったようです。


次は、グループワーク。物語の世界から架空の香水を創造しました。小川洋子さんの小説『凍りついた香り』より、登場人物の調香師が記録していた、香水のイメージとなる言葉を紹介。この言葉から感じる温度や湿度・明暗や雰囲気を考えてから、香水を作るならどのような香りを入れたいか、グループで考えてもらいました。
素敵なアイディアをいくつかご紹介します。
①「締め切った書庫。埃を含んだ光」
・オレンジ、ジャスミン、メープルシロップ
・シナモン、ナツメグ、パイナップル、メープルシロップ
・金木犀、コーヒー、ヒノキ
・血液、ヒノキ、バニラ
②「凍ったばかりの明け方の湖」
・ミント、シトラスをベースに、杉、石けん、プールの匂い、ローズマリーなど
・森、ムスク、レモングラス、土
・ミント、シトラス、獣
・木、ミント、りんご、おひさまの香り
私も思いつかないような組み合わせがたくさん出てきました。中高生の感性に脱帽です!!!!!!
そして最後に、自分の大切な香りや思い出の香りから、架空の香水を考えてもらいました。
中高生の皆さんには、五感を研ぎ澄ませ、心を震わせ、様々な経験の引き出しを作ってもらいたいと思っています。
引き出しが多いほど、人から受け取る情報の解像度が高まります。音楽・文学・全ての芸術をより深く楽しむことができるでしょう。そして引き出しが多いほど、自分が感じたことを的確な言葉で、さらに相手に伝わるように表現することができます。
五感を鍛えることで共感力やコミュニケーション力を高めてほしい、そして何より、日々のささやかの幸せに気付き、心豊かな生活を送れるようになってほしいということが私の願いです。
教養講座では、普段の授業とは異なる視点から生徒のみずみずしい感性に触れることができ、教員としても多くの学びを得ています。
参考文献 小川洋子著 『凍りついた香り』 2001年 幻冬社
